学習ログ一覧ページを作成しよう
- 学習の目標
- はじめに
- Controller の修正
- View の実装
- ナビゲーションバーにリンク追加
- 投稿後のリダイレクト先の変更
- System Spec の修正
- 動作確認
- テストの追加
- テスト実行
- 変更をコミット
- まとめ
学習の目標
本章では、以下の内容を学習します。
- 投稿一覧を表示するためのコントローラーアクションの実装方法を理解する
- 複数の投稿を表示するビューの作成方法を習得する
- ナビゲーションバーへのリンク追加方法を学ぶ
- リダイレクト先の変更とテストの更新方法を理解する
はじめに
今回は、投稿した学習ログの一覧ページを作成していきます。ユーザーが登録した学習ログを一覧表示することで、過去の学習内容を振り返ったり、他のユーザーの学習内容を参考にしたりすることができるようになります。
具体的には、index アクションを実装して投稿一覧を表示するビューを作成します。また、ナビゲーションバーにリンクを追加することで、ユーザーが簡単に投稿一覧ページにアクセスできるようにします。
Controller の修正
まずは、PostsController の index アクションを修正します。これまでは空の状態でしたが、投稿一覧を表示するための機能を追加しましょう。
app/controllers/posts_controller.rb
def index @posts = Post.limit(10).order(created_at: :desc)endこのコードでは、 Post モデルから最新の投稿を10件取得し、@posts というインスタンス変数に格納しています。
limit(10) メソッドは、取得するレコードの数を制限し、order(created_at: :desc) メソッドは、作成日時の降順で並べ替えています。
created_at は、Rails が自動的に生成するカラムで、レコードが作成された日時を保持しています。desc は降順を意味し、最新の投稿が最初に表示されるようになります。
この2つのメソッドを組み合わせることで、最新の投稿10件を取得できます。
View の実装
次に、index アクション用のビューファイルを実装します。以下のコードをapp/views/posts/index.html.erbに追加してください。
<div class="space-y-6 w-3/4 max-w-lg"> <label class="block text-xl font-bold text-gray-700">学習ログ一覧</label>
<div class="items-center justify-center"> <% @posts.each do |post| %> <div class="focus:outline-none mb-7 bg-white p-6 shadow rounded"> <div class="flex items-center border-b border-gray-200 pb-6"> <div class="flex items-start justify-between w-full"> <div class="pl-3"> <p class="focus:outline-none text-lg font-medium leading-5 text-gray-800"><%= link_to post.title, post_path(post) %></p> <p class="focus:outline-none text-sm leading-normal pt-2 text-gray-500">by <%= post.user.nickname %></p> </div> </div> </div> <div class="px-2"> <p class="focus:outline-none text-sm leading-5 py-4 text-gray-600 line-clamp-3 overflow-hidden"><%= post.content %></p> </div> </div> <% end %> </div></div>このビューでは、コントローラから渡された投稿データを @posts.each を使ってループ処理し、それぞれの投稿を表示しています。実装のポイントは以下の通りです。
まず、@posts.each を使って、取得した投稿データをループ処理しています。各投稿は post という変数で参照されます。
次に、link_to メソッドを使って、投稿のタイトルをクリックするとその投稿の詳細ページに遷移するようにしています。post_path(post) は、Rails のルーティングヘルパーで、指定した post の詳細ページへのパスを生成します。
さらに、投稿の内容は line-clamp-3 クラスを使用して、3行まで表示し、それ以降は省略されるようにしています。これにより、長い投稿内容でも一覧ページが見やすくなります。
最後に、投稿の作成者のニックネームを表示しています。post.user.nickname を使って、関連するユーザーのニックネームを取得しています。
このビュー実装により、投稿一覧が適切にフォーマットされ、各投稿の重要な情報が一目で把握できるようになります。
ナビゲーションバーにリンク追加
ユーザーが簡単に投稿一覧ページにアクセスできるように、ナビゲーションバーにリンクを追加します。投稿一覧はログイン状態に関わらず閲覧できるため、ログイン判定の外に配置します。
app/views/shared/_navbar.html.erb
<ul class="flex flex-col mt-4 md:flex-row md:space-x-8 md:mt-0 md:text-sm md:font-medium"> <!-- ここから追加 --> <li> <%= link_to "ログ一覧", posts_path, class: "block py-2 pr-4 pl-3 text-gray-200 hover:text-white border-b border-gray-700 hover:bg-gray-700 md:hover:bg-transparent md:border-0 md:hover:text-blue-white md:p-0" %> </li> <!-- 追加ここまで --> <% if current_user %> <!-- 既存のログイン時メニュー -->この変更により、ナビゲーションバーに「ログ一覧」というリンクが追加され、クリックすると投稿一覧ページに移動できるようになります。
投稿後のリダイレクト先の変更
これまでは投稿成功後にトップページにリダイレクトしていましたが、今回は投稿一覧ページにリダイレクトするように変更します。
app/controllers/posts_controller.rb
def create @post = Post.new(post_params) @post.user_id = current_user.id if @post.save flash[:notice] = '投稿しました' redirect_to posts_path # トップページから投稿一覧ページへ変更 else flash[:alert] = '投稿に失敗しました' render :new endendこの変更により、ユーザーが投稿した後すぐに自分の投稿を含む一覧ページを確認できるようになります。ユーザー体験として、投稿後にすぐに他の投稿も見たいというニーズに対応しています。
System Spec の修正
投稿後のリダイレクト先を変更したので、テストも更新する必要があります。以下のように修正してください。
spec/system/posts_spec.rb
context 'パラメータが正常な場合' do it 'Postを作成できる' do expect { subject }.to change(Post, :count).by(1) expect(current_path).to eq('/posts') # ルートパスから投稿一覧パスへ変更 expect(page).to have_content('投稿しました') endendこれで、テストも新しい動作に合わせて更新されました。
動作確認
実装が完了したら、実際に画面で動作を確認してみましょう。
ナビゲーションバーの確認
開発用サーバを起動し、ナビゲーションバーに「ログ一覧」リンクが追加されていることを確認します。
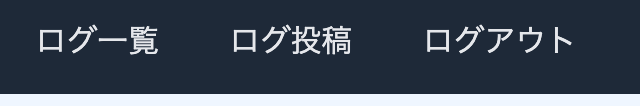
投稿一覧の確認
「ログ一覧」リンクをクリックすると、http://127.0.0.1:3000/posts へアクセスして投稿の一覧画面が表示されます。

投稿後のリダイレクト確認
新規投稿ページから投稿を行うと、投稿一覧ページへ自動的にリダイレクトされ、投稿成功のメッセージが表示されることを確認します。
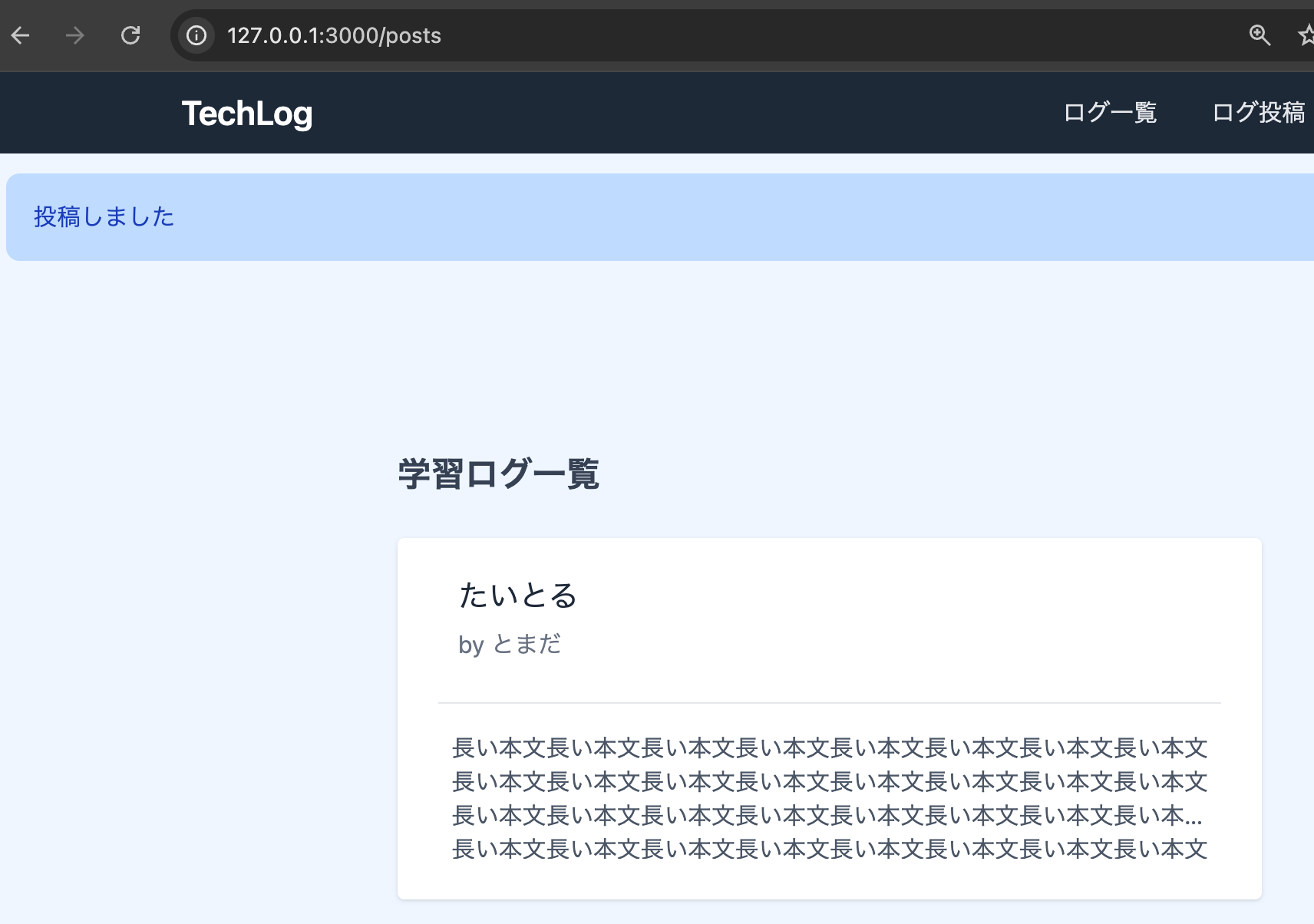
テストの追加
新しく実装した機能を保証するためのテストを追加しましょう。
Request Spec の追加
一覧ページへのアクセスを確認するためのテストを追加します。
spec/requests/posts_spec.rb
# ...describe 'GET /posts' do context 'ログインしていない場合' do it 'HTTPステータス200を返す' do get '/posts' expect(response).to have_http_status '200' end end
context 'ログインしている場合' do it 'HTTPステータス200を返す' do sign_in @user get '/posts' expect(response).to have_http_status '200' end endendこのテストでは、ログイン状態に関わらず投稿一覧ページにアクセスできることを確認しています。
System Spec の追加
投稿一覧の表示内容を確認するためのテストを追加します。
spec/system/posts_spec.rb
# ...describe 'ログ一覧機能の検証' do before do # 事前にもう一つの投稿を作成 @post2 = create(:post, title: 'RSpec学習完了 2', content: 'System Specを作成した 2', user_id: @user.id) visit '/posts' end
it '1件目のPostの詳細が表示される' do expect(page).to have_content('RSpec学習完了') expect(page).to have_content('System Specを作成した') expect(page).to have_content(@user.nickname) end
it '2件目のPostの詳細が表示される' do expect(page).to have_content('RSpec学習完了 2') expect(page).to have_content('System Specを作成した 2') expect(page).to have_content(@user.nickname) end
it '投稿タイトルをクリックすると詳細ページへ遷移する' do click_link 'RSpec学習完了' expect(current_path).to eq("/posts/#{@post.id}") endend# ...このテストでは、複数の投稿が一覧ページに表示されることと、タイトルをクリックすると詳細ページに遷移することを確認しています。
また、投稿成功時のリダイレクト先も変更したので、「ログ投稿機能の検証 > ログインしている場合 > パラメータが正常な場合」の既存テストも修正します。
context 'パラメータが正常な場合' do it 'Postを作成できる' do expect { subject }.to change(Post, :count).by(1) expect(current_path).to eq('/posts') # 修正 expect(page).to have_content('投稿しました') endendテスト実行
最後に、すべてのテストを実行して問題がないことを確認します。
$ bin/rspec
Finished in 1.22 seconds (files took 0.18695 seconds to load)56 examples, 0 failuresすべてのテストが通過していれば、実装は正常に完了しています。
変更をコミット
ここまでの変更をコミットしておきましょう。
$ git add .$ git commit -m "学習ログ一覧ページを作成"$ git pushまとめ
本章では、TechLog アプリケーションに学習ログの一覧ページを実装しました。学んだ内容は以下の通りです。
limitとorderメソッドを使って、データベースから取得するレコードを制限し並べ替える方法- 投稿一覧を表示するためのビューを作成する方法
- ナビゲーションバーにリンクを追加してユーザーの利便性を向上させる方法
- リダイレクト先を変更してユーザー体験を改善する方法
- 実装した機能に対するテストの追加と修正方法
これらの機能により、ユーザーは投稿した学習ログを一覧で確認できるようになり、アプリケーションの使いやすさが大幅に向上しました。次回は、投稿の削除機能を実装していきましょう。
Basicプランでより詳しく学習
この先のコンテンツを読むにはBasicプラン以上が必要です。より詳細な解説、実践的なサンプルコード、演習問題にアクセスして学習を深めましょう。